宮里先生とのドイツ調査(3)
田中 誠(弁護士)
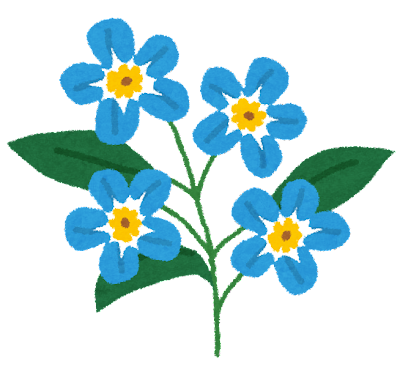 さて、弁護士グループの海外調査というと、観光要素が大きいこともあるのだが、労働弁護団の場合は、かなり真面目なものであることが多い。
さて、弁護士グループの海外調査というと、観光要素が大きいこともあるのだが、労働弁護団の場合は、かなり真面目なものであることが多い。
特に、このドイツ班は、団長の宮里先生を中心に、「硬派」のメンバーがそろっていたので、事前準備もきっちりやったし、現地でも、公的機関が休んでいる土日以外は、連日勉強していた。
無論、調査以外の要素がなかったわけではなく、夜は必ずフリーなので、メンバーで地元の普通の店に食事に行って現地のビールを飲みながら、その日の調査を振り返るのを常としており、これを機にドイツ各地のビールのファンになる者は多かった(特にケルンでの「ケルシュ」が人気だったように思う)。
夜の会では、笑顔の宮里先生から、いろいろな話を伺ったのだが、労働弁護団の多くの先輩方とも共通するが「俺たちの若い頃は」的な話はなく、上から目線の指導も無く、宮里先生を中心とする暖かい会話の輪となっていた。
筆者が、白アスパラガスの注文に躊躇(日本の瓶詰め・缶詰めの先入観から)していたところ、「田中君。全く違うものだから、試してみた方がいいよ」と「指導」を受けたことはある(正しい指導だった)。
また、調査以外の要素として大きかったのは、これも宮里先生の発案で、統一(1990年)により訪問しやすくなった旧東独地域を見ようということで、あえて東独地域に滞在する行程を組んだということがあった。カッセルのBAG訪問のための滞在地も、少し離れたアイゼナハ(チューリンゲン)にして、同地には調査予備日含め3泊した。
統一後7年の当時、まだ旧「国境」地帯には監視小屋様の建物が散在しており、ここが旧「国境」かという地点を過ぎると、アウトバーンは急に舗装が悪くなって、バスはガタガタ揺れ、チャーターしたフランクフルト・アム・マインのバスの運転手が毒づいていた。
アイゼナハには、まだ世界遺産に登録されていなかったヴァルトブルク城があるが、見学者は私達以外は誰もおらず、その雰囲気は、ルターがこもっていた16世紀のままの幽玄なものとも言えるし、陰鬱とも言えた。街自体も、地味で暗く、特に夜は暗く、中世の街のごとしだった。筆者個人的には嫌いな感じではなかった。
予備日が空いたので筆者一人で訪れたライプツィヒは、都会で、大分感じが異なり、駅頭で屈強な男性達がアメリカのアクション映画のチラシを配っていて、「We are American.」などとやっていたし、バドワイザーを出す店が若者で大混雑していた。「ビールならドイツビールの方が明らかに上なのに、それでも若者にはアメリカなのか」と、「西側」の影響力を感じた。
社会主義の優等生と言われた東ドイツが、完全に西ドイツに吸収合併される形となり、しかも格差が露骨であることについては、夜の食事の席で、いつも話題になり、世代によって感じ方はかなり違い、宮里先生と筆者でもかなり感想は異なった。
なお、5年後に個人的に再訪した際には、アイゼナハは西ドイツの街とあまり変わらない明るい街になっており、ヴァルトブルク城は観光客で大混雑していた。
この「欧州労働紛争処理システム調査」後、ドイツ班のみ独立した調査報告書冊子を作成・頒布した。また、宮里先生ほかドイツ班メンバーのドイツ学習熱の高まりは続き、まもなく設立された日独労働法協会に、メンバーからは最終的に7名中6名の弁護士(発起人であった宮里先生と筆者のほか4名)が入会することとなった。
労働弁護団は、この調査結果を重要な根拠の一つとして、当時の司法改革論議の中で、参審制の、単なる調停ではなく判定機能を有する個別的労使紛争解決制度を構築すべきという主張を強め、参審制の完全な実現は果たせなかったものの、労使委員の参画する労働審判制度へつながった。
筆者個人は、本調査の後、筆者世代の中では労働委員会事件を比較的多く担当していることから、宮里先生の主宰する労委労協(全国労働委員会労働者側委員連絡協議会)の労働委員会命令研究会をお手伝いすることとなった。
そして、不当労働行為制度・労働委員会制度の研究を推薦理由として、労働法学会への入会推薦もしていただき、日独労働法協会の理事は宮里先生の後継という形になっている。
むろん、宮里先生は労働弁護士の先輩として大きな存在で、筆者は到底その場所を埋めることはできないが、せめて、限られた分野だけでは(労働委員会の不当労働行為救済命令の研究、ドイツ法研究者の方々と労働弁護士の橋渡し役)、亡き宮里先生の衣鉢を継ぐ者として、恩返しをしたいと思っている。
(2023/5/18)
